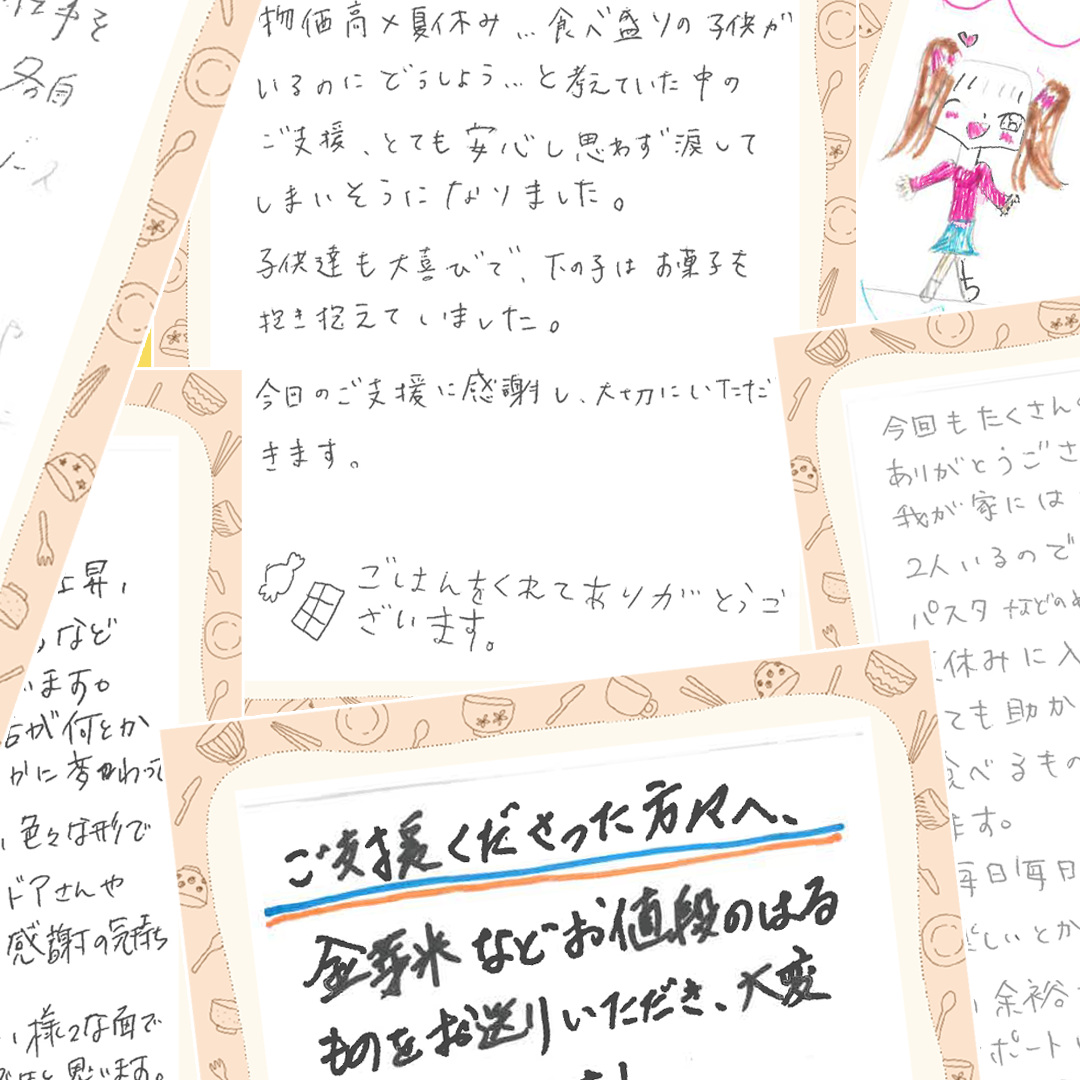あなたの一歩で命を繋げていく|ジャパンハート新病院設立プロジェクト

SUSTAINABILITY

2024年10月より始まった「ORBIS ペンギンリング プロジェクト」。プロジェクトを通してお客様から頂いたたくさんの寄付ポイントを寄付金として、オルビスから各パートナー団体にお届けしています。
その大切な想いをのせた寄付金は団体でどのように活用されているのでしょう。 活用の様子を皆さんにお伝えしたいと思い、私たちは特定非営利活動法人ジャパンハート(以下、ジャパンハート)の東京事務所を訪れました。
ジャパンハートは、開発途上国を中心に医療活動を行っている日本発の国際医療NGOです。 2025年10月には、カンボジアの首都近郊で新たな医療拠点「ジャパンハートアジア小児医療センター」を開設予定。このプロジェクトのリーダーを務める、ジャパンハート事務局長 佐藤抄さんからお話を伺いました。
取材の中で、寄付支援は世界と自分を繋ぐ重要な架け橋になっているというお話も。 ぜひ、寄付をされた方も、寄付を迷われている方も、その1ポイントの寄付支援が想像以上の大きな力になっていることを感じていただきたいと思います。

▲「ジャパンハートアジア小児医療センター」完成予想図
まず、皆さまからの支援について、佐藤さんからメッセージを頂きました。
「私たちジャパンハートの医療支援活動は、単に命を救うことにとどまりません。すべての人が『生まれてきてよかった』と思える社会を作ることを目標としています。どう生きるかで、ひとの人生の質は決まっていくとジャパンハート創設者である𠮷岡秀人も言います。
ご支援は大きな助けになります。寄付は、社会とつながることでもあります。ご支援を通して皆さんは社会とつながり、そのつながりが社会全体の幸福に結びついていくのです。本当に感謝しています。」
佐藤さんは続けます。「医療は単なる手段にすぎません。私たちが目指しているのは、誰かのために役立ちたいと思う人が、自分自身の人生の質を高めることです。誰かのために何かをすることで、そこに『生まれてきてよかった』と感じるサイクルが生まれ、個人がその力を社会に還元する、そんな循環を作り出したいんです。」

もちろん、医療支援を継続的に行うためには、物資や医薬品だけでなく、医療施設の運営や人材の確保など、多岐にわたる領域での費用が必要になります。「今直面している課題は、資金と人材の確保だ」と佐藤さんは言います。特に新しい医療拠点の設立や医療スタッフの育成には、長期的な視点での大規模な資金が求められます。それらの活動を続けるためには、支援者の理解と、寄付による協力が欠かせません。
資金的にも、人材の面でも、そんなに大変な新病院の設立にジャパンハートが取り組む理由は一体なぜなのか。佐藤さんの生い立ちを追うことで、ジャパンハートが目指すビジョンとの繋がりが明らかになっていきました。
𠮷岡医師との出会いに導かれて
佐藤さんは、会社経営者の母が運営している支援基金の様子を間近で見て育ちました。その関わりから、支援先に実際に訪れて現地の活動の様子を確認することも多かったそうです。
2004年頃。ジャパンハートの活動を視察するためにミャンマーへ渡り、そこで初めて、ジャパンハートの創設者である𠮷岡医師に出会いました。それが佐藤さんにとって一つ目の転機となりました。
「𠮷岡の医療に対する姿勢と、患者さんの心まで救いたいという強い思いに衝撃を受けました。“こんな日本人がいるのか”と心を打たれました。」
「私は子どもの頃、父をがんで亡くしています。その時の病院での父の扱われ方が、子ども心に “大切な人が尊重されていない”と感じるもので、いやだった。それから、病院は怖い場所だという印象を強く持っていたんです。ところが、𠮷岡の医療に対する考え方や患者への考え方を聞いた時、医者に対する長い間の不信感が解け、心が癒され救われたように感じたんです。」
その瞬間、佐藤さんは「この活動を応援し、広げていきたい」と感じたそうです。
「泣くことなんて普段全く無い私が、そのときは涙が止まらなかった。それほど鮮烈な体験でした。」

その後、2011年の東日本大震災で佐藤さんに二つ目の転機が訪れます。何かできることはないかと、ジャパンハートの活動拠点を手伝うことに。しかし抱いた強い思いとは裏腹に、現地では自分の無力さに打ちのめされます。「スタッフからはすごく感謝してもらえたけれど、何の達成感も残らなかった。情けなくて、事務所の外で1人泣いたのを覚えています。」
その経験から「ただ一時的に手伝うだけでは本当の支援にはならない。腰を据えて、しっかりと行動を起こさなければ何も変わらない。」と思いを新たにします。
それまでの仕事を辞め、ジャパンハートで本格的に活動することを決意したのです。
子どもの命と向き合う中で直面した課題
カンボジアに建つ新たな病院は、ジャパンハートが持つ自前の病院としては2拠点目になります。新たな病院を設立する背景について、佐藤さんにお伺いしました。
カンボジアは、歴史的事情から医療水準が非常に低く、人々には医療への不信感も広がっていました。病院で診察を受けたことがないという人も珍しくありません。そんな中で「日本から来た」という信頼感も手伝い、ジャパンハートの巡回診療支援には多い時に400人もの患者が押し寄せる毎日。当初は手ごたえを感じていた巡回診療ですが、次第に大きな課題に直面します。
「それは、短期間では治せない患者が出てきたこと。特に小児がんの子どもたちは、数週間の滞在だけではどうすることもできません。『ごめんね、うちでは治療できない』と伝えるのは非常に辛かった。日本の病院に連れて行くこともあったが、全員にそうできるわけではない。資金面や家族の負担を考えるとどうしても支援の手が届かない子どもが多かったのです。」
この課題に、ジャパンハートは「自分たちで病院を作ろう」と決意します。そして、2016年にカンボジア国内では1拠点目となる、小児がん治療が可能な病院を設立しました。 しかし、カンボジアには小児がんを治療できる施設がほとんど無いことから、そこはすぐに満床に。より多くの子どもたちを救うためには、キャパシティを拡大する必要がありました。

誰もが行きたくなる、テーマパークのような病院づくり
「開発途上国と先進国の医療には大きな格差があります。生まれた場所が、飛行機でたった十時間移動する距離の違いだけで、助かる子どもと助からない子どもの差が生まれる。つまり、命の格差が生まれてしまう現実がある。」佐藤さんの声には熱がこもっていました。「生まれた場所で命が決まるなんて、あってはならない。」
「来てくれた患者を治すだけでなく、そもそもまずは病院に来てもらわなければいけません。病気の早期発見は、その後の生存率を大きく左右するからです。そのためには、病院自体を『行きたいと思える場所』にする必要があると考えています。たとえば、遊びに行くついでに検診を受けるような、そんな風に病院に足を運びたくなる仕掛けを作りたいんです。」
命の格差という簡単には埋めがたい現実に向き合いながら、佐藤さんの構想は壮大で前向きでした。
「𠮷岡は、ガチャガチャコーナーがあったり、ゴーカートで院内を走れるようにしたいと言っていました。長期入院している子どもたちにも楽しいと思える、「心を救う医療」を提供できるようにしたいと。絶対に看護師さんから怒られそうですけどね。」佐藤さんからも笑みがこぼれます。

子どもたちの命と、そして仲間の心も救いたい
現在はカンボジアと日本を行き来しながら、新病院の設立をスピード感を持ってリードしている佐藤さん。設立には莫大な資金が必要であり、内部からは「支援が十分に集まってからでいいのでは?」や「なぜ急ぐのか?」という意見も出たといいます。
それでも佐藤さんは、ひとつの思いから動き続けました。「早く設立すれば、それだけ助けられる命が増える」。

医療体制を整えて助けられる子どもが増えたと言っても、まだ5割ほどは助けられずつらい思いを噛みしめる日々。残念ながら病院で助けられなかった子どもたちを送り出すとき、車が見えなくなるまで皆で祈りを捧げるのだと言います。
「次に生まれてくる時には、ちゃんと健康で大きくなれますように」――
誰もが涙をこらえ、つらい気持ちを抱えながら心の中で祈り続けます。そんなスタッフたちの背中を見て、佐藤さんは新病院へ思いを募らせます。
「自分はパソコンで作業をしていることが多く、子どもたちとも距離をおくことができる。けれど医療スタッフはそうはいかない。しんどいと思う。」佐藤さんは遠くを見つめます。
「これ以上、仲間に悲しい思いをさせたくない、1割でも助かる子どもを増やしたい。助かる子どもが増えれば、こんなシーンがひとつでも減るから。」それが佐藤さんの強い原動力となっています。

すべての人が「生まれてきてよかった」と思える社会へ
こうした佐藤さんたちの活動は、一人ひとりの手を差し伸べる行動から生まれています。小さな一歩が、やがて社会全体を動かす大きな力となり、命を救い、希望をつなげることに繋がっていきます。
「例えば1ポイントでも、寄付をすることで社会の問題に向き合い、解決への一歩をともに踏み出している。それは、社会全体の未来の幸せに繋がるだけでなく、自身の人生の質を上げることにも繋がっている」と𠮷岡さんや佐藤さんは信じています。
皆さまの温かいご支援が、確実に社会を変えていく力になります。私たちと一緒に、こどもの未来を作り、命を守る活動を支えていきませんか。
ジャパンハートへ寄付の支援を行う→こちら(寄付ページ)