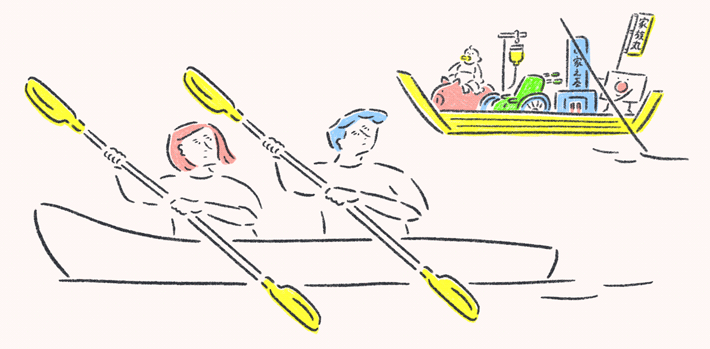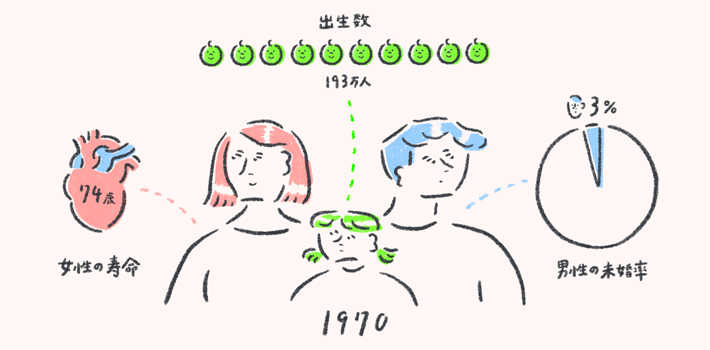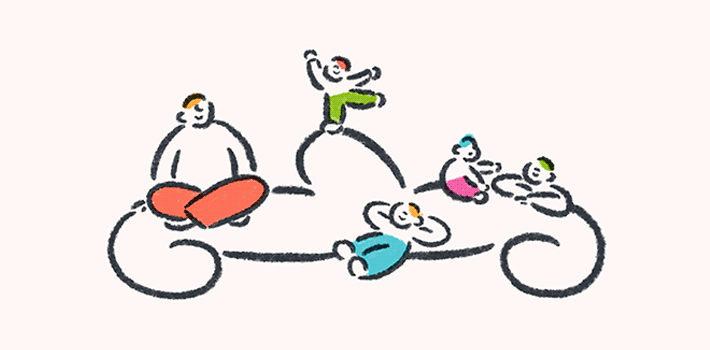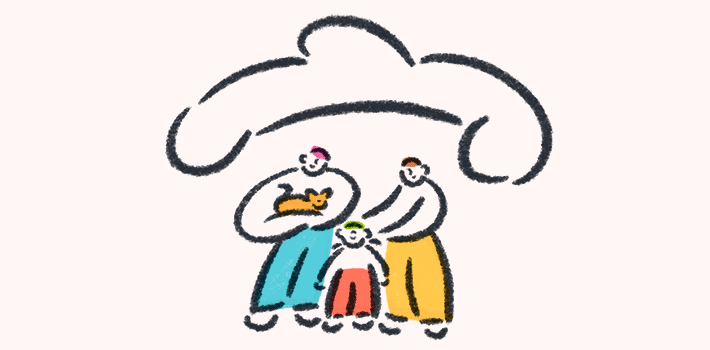小さな社会的物語が語ること|家族編 #01 |佐々木康裕

&Human Nature

アイデンティティや多様性が尊重される社会は、望ましい。しかし、一方でその声は、社会通念や同調圧力という“足かせ”によって、かき消されてしまうことも少なくありません。真にアイデンティティや多様性が尊重される社会に向けて、わたしたちが心に留めておくべきこととはーー。ビジネスデザイナーの佐々木康裕が綴るエディターズレター。
Takramが協力して策定したORBISのブランドパーソナリティ「Compassion-ist」。そのCompasion-istという言葉に込めたのは、他者を理解し、力になりたいという切実な願いだ。
もちろんわたし自身もそうありたいと願うが、多様性を肯定し、他者の苦しみや切実さに寄り添うということの解像度がまだまだ足りないな、と思わされた、二つの印象的なトピックがある。
一つは、とある海外コスメブランドの「母の日」に対する姿勢。
「母の日」には、さまざまなブランドから、大量に広告やキャンペーンのメッセージがメールボックスに届く。そんな中、他社と全く異なる、受け手への配慮と深い理解が感じられるメールの存在が光る。
「もしこの日があなたにとって辛い日であれば、来年以降はメールを送りません」というオプトアウトのボタンが置かれていたのだ(日本語のメールではこの手のことを行っていない。なぜだろうか)。このテキストを読みながら、確かに存在しているはずの、家族と難しい関係にあるなどの理由で「母の日」を快く思わない人に全く思いを寄せることのできていなかった自分に恥じ入ってしまった。
仕事柄、母の日のキャンペーンに何をすべきか、といったことをクライアントのブランドとディスカッションするような機会も少なくない。そうした会話のベクトルは売上など数値に向かいがちで、自分自身も「仕事人モード」に変身して会話を進める。十分な想像力があれば、このメールのような視点を投げかけることができたかもしれないのに、発言の機会や持っているパワーを、そのために使うことができていなかった。
さらに、Webサイトにいくと、その母の定義の仕方にも感銘を受ける。
“いつも頼りになる、時宜を得た心づくしの助言を与え、私たちの人生を見守り、支えてくれる、あらゆる種類の人々”
わたしたちが無意識に前提とする、慈愛と尊敬に満ちた関係ではない、多様な母子の関係が存在する。産みの親ではない、母に虐待を受けていた、死別している、など母をめぐる多くの複雑なコンテクストがある。このメールには、そうした細やかなニュアンスをくみ取り、寄り添おうとする優しさや配慮、加えて、ブランドとして大事にすべき姿勢や芯、強い意志を感じる。

もう一つは、『母親になって後悔してる』〈新潮社〉という衝撃的なタイトルの本だ。
「もし時間を巻き戻せたら、あなたは再び母になることを選びますか?」。著者であるイスラエルの社会学者オルナ・ドーナト(彼女自身も「母親にはなりたくない」と考えている)は、この質問に「ノー」と答えた23人の女性にインタビューを行い、社会的にタブー視されているその感情に丁寧に向き合いながら、彼女たちの複雑な思いに寄り添っていく。
同書はドイツなど世界各国で大きな共感を呼び、ソーシャルメディア上で #regrettingmotherfood というハッシュタグのもとに議論が交わされた。もちろん中には多くの怒りや反感も含まれる。社会や世間は、アイデンティティや多様性を重視し、自由に生き方を選んでいい、というフリをしながらも、ある枠を越える選択をすることに対して眉をひそめたり非難の声を上げたりする。「母親であること」は神聖なものであり、女性はそれを後悔すべきではない、という社会的物語(ソーシャルストーリー)が社会を覆っている。そして、それは個人のストーリーより優先されがちだ。
フェミニストであり哲学者のダイアナ・ティージェンス・マイヤーズは、それを「想像力の植民地化」と呼んでいる。私たちの想像力は社会通念や同調圧力といったさまざまな鎖に縛られており、特定の選択をするように仕向けられている。オルナ・ドーナトは「母親」という枠において、こうした問題を提起しているが、身体のこと、性別のこと、仕事のことなど、その他の多くの場面や状況に対して、こうした「社会的物語への不適合による苦しみ」が潜んでいるのではと思うのだ。
少し前に、アメリカのドラマ『Modern Love』で、概日リズム睡眠障害という、昼夜逆転の生活しかできない人の存在を知った。登場人物の女性は昼間にカフェに行ったり、日光の下で海水浴をしたりするという普通の恋愛ができない。映画『万引き家族』に登場する主要人物の父親の治については境界知能を示唆する描写がいくつかある。世界は、そうした難しいストーリーに溢れている。わたしたちはそういった存在に心を寄せることができているだろうか。
この企画では、こうした大きな社会的物語からこぼれ落ちそうな人やことの存在に目を向けていきたい。ORBISが真のCompasion-istになるためには、普通の人が見過ごしてしまいそうな、小さな苦しみ、悩み、あるいはささやかなプライドや自信にこそ目を向ける必要があるように思う。
加えて、自分自身を救い、他者を救うために、わたしたちの想像力を脱植民地化する必要がある。この企画は、そうしたことへの理解を通じて、ORBISが繊細な寄り添い方を積み重ねるブランドに進化するための手がかりを増やしていく取り組みにしたい。