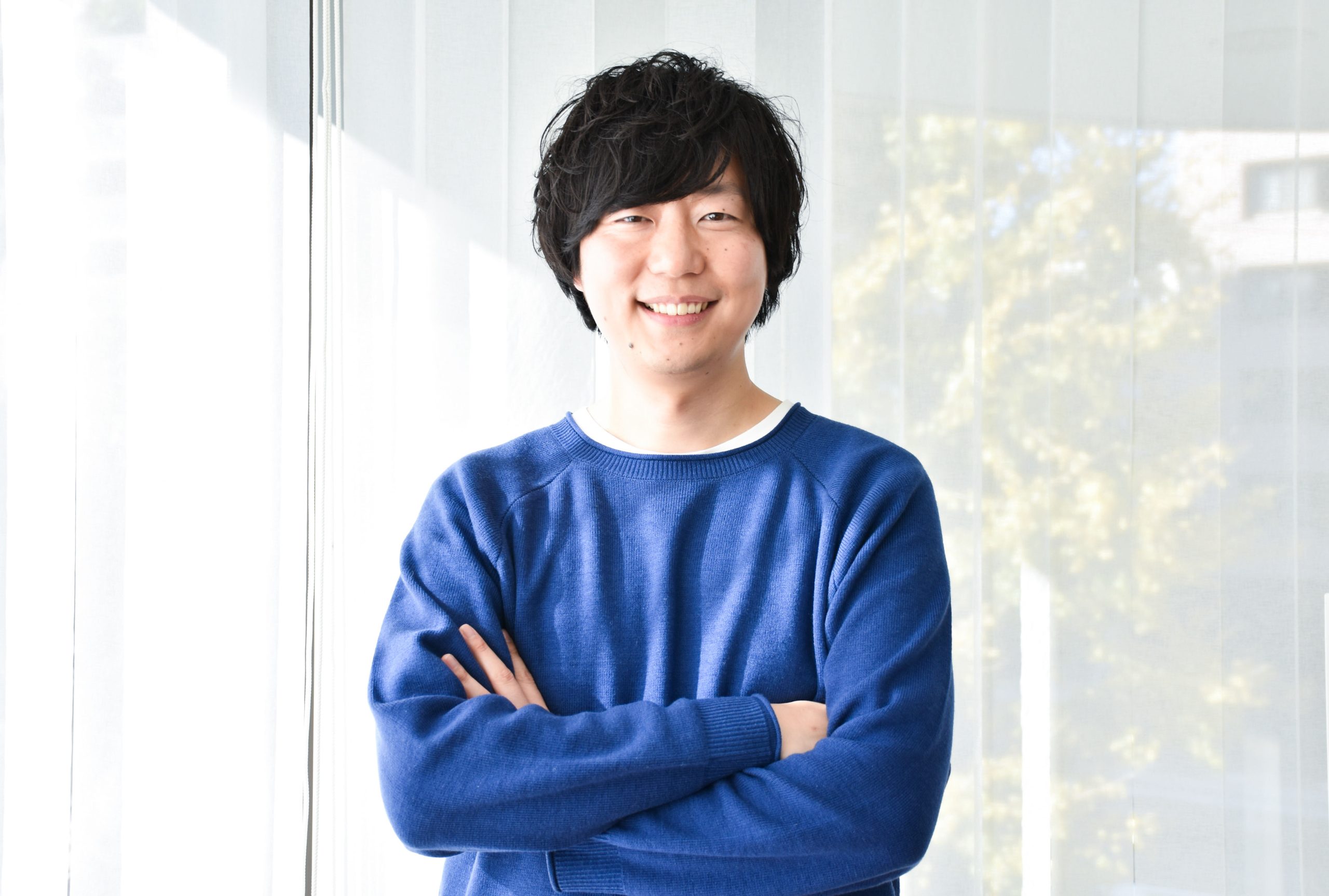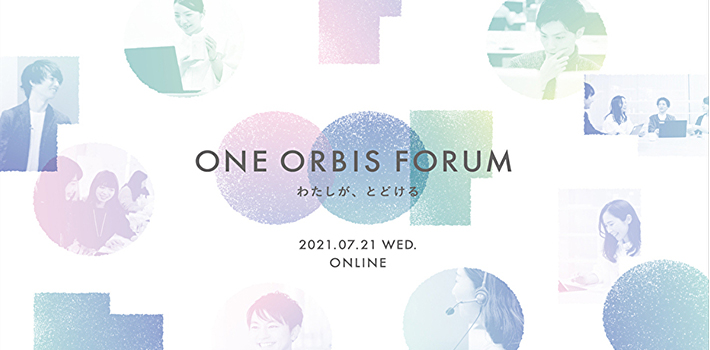オルビスが週2日出社の「ハイブリッドワーク」を導入した背景、狙いとは?

JOB&CULTURE

こんにちは。オルビス公式ブログ担当の土井山です。
オルビスでは、新たなチャレンジが連続的に生まれやすい「未来志向×オープンマインド」なカルチャーの加速を目指して、オフィス出社とリモートワークを組み合わせた「ハイブリッドワーク」を導入しています。そして、社員一人ひとりが最大のパフォーマンスを発揮できる働き方の実現に向けて決めた具体的方針が、週2日をオフィス出社、残り3日間はオンライン・オフラインの働き方をフレキシブルに選択できる新しいワークスタイルです。
2022年よりスタートしたこの取り組みの大きな特長の一つは、出社日のうち1日(火曜日)を「ONE ORBIS DAY(OOD)」として、本社社員の全員がオフィスで働く日を設定したことにあります。
今回の記事では、経営ボードが何度も議論を重ねて新方針の導入に至った背景、週1日を「OOD」と定めた理由など、オルビスのハイブリッドワークについて役員3名に聞きました。
ぜひご一読ください。
ハイブリッドワーク導入の裏側について、役員3名にインタビューしました
リモートワークを実施して明らかになった、メリットと課題
コロナ禍以降、オルビスの本社社員はリモートワークが中心の働き方に移行しましたが、どのような変化や課題がありますか?
元木:コロナの状況からリモートワーク中心の働き方に移行したことで、個人やグループ単位で行う業務においては円滑に遂行することができています。一方、ビューティーブランドとして情緒的価値でお客様の心を掴むような企画を立案・進行していくなかでは、オンラインよりもオフラインのコミュニケーションの方が効率的であり、生産性も高まると実感しています。
これは私の息子を見ていて思ったことですが…(笑)。インプット型の勉強はオンライン授業で十分完結することができている一方、部活動でも同様の方法で勝てるチームを作れるかというと、オンラインのコミュニケーションでは一体感を醸成するのに限界があります。ゼロから1を生み出すには、ノンバーバルを含むリアルなコミュニケーションも大事だと気づかされました。

西野:2020年4月に最初の緊急事態宣言が発令されて、いきなりほぼリモートワークを強いられる状態になりましたよね。その時にまず驚いたのが、カタログ(オルビスマガジン)の色見チェックや開発商品のサンプル確認など、これまで当たり前のようにオフィス出社で行っていた数々の業務を、出社制限がありながらも手段を変えて引き続き遂行できていたこと。これは社員の変化対応力の高さゆえであり、本当に素晴らしいことだと思っています。
一方で、元木さんが言う通り"これまで通りに業務を遂行する"だけでは、新しい価値が生まれづらくなるだろうという課題に対して、新しいブランド体験を創出し続ける"勝てる組織"にしていくために何ができるかを経営陣で考え、社員にとってベストな働き方を議論してきました。
福島:オルビスは、肌が本来持つ力を引き出し、自分らしく、ここちよく年齢を重ねていこうという「スマートエイジング®」をお客様への提供価値としています。このフィロソフィーが軸にあるからこそ、コロナ禍においても社員一人ひとりが「お客様との繋がりを大切にし、この価値をお届けしたい」「オルビスに貢献したい」という想いを持ち続けているのだと思います。
とはいえ、強い想いがありながらも実際にはオンラインのコミュニケーションが続くと、全社で連動しながらお客様へ価値をお届けするためのつながりを感じにくいという課題も生じていると思います。自分自身の見える範囲が狭まり、全体の動きがイメージしづらくなったことで、社員一人ひとりが持つ多様な力を組織全体で活かせなくなってきているように感じています。
ーーコロナ禍で入社した社員についてはいかがでしょうか。

福島:新卒・中途を問わずさまざまな個性やバックグランドを持つ社員がオルビスへ入社し、入社後は早期戦力化を目指して一人ひとりに寄り添う独自のオンボーディングを実施しています。
コロナ禍を経て、(社内向け)事業戦略セミナーや各グループで行われる業務の引継ぎなどの体系的な情報はオンラインでも効率的にインプットすることができています。しかしながら、先ほど述べたことにもつながりますが、自身の所属するグループ以外の情報や社内の雰囲気など、会社全体の現状把握には時間がかかってしまう状況です。
西野:リアルなところで言うと、会社の廊下で社員とすれ違うことや同じエレベーターに乗り合わせる機会も減ってしまったことで、新入社員だけでなく私たち自身も横断的なコミュニケーションが生まれづらく、「誰が、何を知っているのか」という情報を把握しづらくなってしまいました。
元木:入社したばかりで分からないことの方が多いなか、会社にいれば、チャットで文字を打たなくても近くに座っているメンバーを頼ることができますよね。実際に、業務を習得して自走できるまでのオンボーディングをフルリモートで行う場合と、週1~2日は対面で行う場合とでは、後者の方がオルビスでの仕事や働く環境に慣れるまでのスピード感が圧倒的に速いことが分かりました。オンボーディングをする側、受ける側の双方にとって、分からないことを対面で解消できることの安心感もあると思います。
こうした背景から検討を重ねた結果、オンラインとオフラインの良さを掛け合わせた「ハイブリッドワーク」がオルビスのカルチャーにフィットしており、サステナブルに新しい価値を生み出すことのできる働き方ではないかということになりました。
関連記事
「一人ひとりの力を最大化する」ために。中途社員を早期戦力化へ導く、オルビスのオンボーディング
https://corp.orbis.co.jp/article/interview_on-boarding22/
”遂行する”だけではなく、新しい価値を生み出す、"勝てる組織"への挑戦
ーーオルビスの「ハイブリッドワーク」について、週2日をオフィス出社、そのうち1日を「ONE ORBIS DAY(通称:OOD)」として全員出社にしたのはなぜですか?

西野:私たちはお客様一人ひとりに寄り添い伴走し続けるブランドとして、個人やグループ単位だけで価値を生み出すには限界があると考えており、「ONE ORBIS」でブランド体験を最大化させることを大切にしています。
コロナ禍の影響拡大のなか、多くの社員に生じた働き方の変化にも、一人ひとりが柔軟に対応できたことで、リモートワークでも一定の成果を生み続けることができています。しかしながら、社員同士のトランザクティブメモリー*が低下し、特に私たちが重要視している部署の垣根を超えた連携が起こりづらくなっていたのも事実です。このトランザクティブメモリーを高めていく手段の1つとして、週1日を「ONE ORBIS DAY」とし、本社の全社員が出社して顔を合わせる日を設定しました。
*トランザクティブメモリー(Transactive Memory)
組織を構成するメンバーが同じ知識(What)を記憶するのではなく、「誰が何を知っているのか(Who Knows What)」という情報を把握することを重視する考え方のこと。
福島:OODでは本社社員全員が出社し、オフィスの至るところで顔を合わせての議論が生まれることで、オンライン会議では得られない会話のスピード感、言葉の背後にある想いや価値観をくみ取ることができますし、オルビスにジョインしてから日が浅いメンバーにとっても、OODを通してこれまで以上にオルビスの組織やビジネスの現状理解、社内の雰囲気を掴みやすくなると思います。
ーーハイブリッドワークの導入により、期待することはありますか?
福島:オフィス出社とリモートワーク、それぞれのメリットを上手く組み合わせて活用することで、「ONE ORBIS」で新しい価値創造が生まれていくことを期待しています。
私の管掌する管理系の部門においては、一見フルリモートで完結する個人作業が多いと思われるかもしれません。しかし実際には、事業を推進するパートナーとして最も広く他部門との接点があります。オルビスは企画から販売までを一貫して行うブランドだからこそ、オフィス出社とリモートワークという選択肢を設けて柔軟性のある働き方にすることで、各部署が連携しやすくなるような環境や風土を醸成していきたい。そして、全社員一人ひとりが最大限のパフォーマンスを発揮でき、組織としても活かせるような仕事ぶりに期待したいと思います。
もちろん、週2日オフィス出社という現在の働き方が最終の完成形ではないので、今後も一人ひとりが多様な個性を発揮することのできる、オルビスらしい働き方を目指してアップデートを続けていきます。
元木:オルビスは約250名の本社社員だけでなく、店舗のビューティーアドバイザー、コールセンターで活動するビスタさんを含む多くのメンバーで成り立っており、実際に日々出勤し現場でお客様に寄り添っています。
企画職の社員はハイブリッドな働き方にはなりますが、何か新しいことに取り組む際にはぜひ、リモートではなくリアルな現場を体感しながら、メンバーたち自身が「この企画、楽しそうだな」と感じてワクワクするような提案をしてほしいです。リアルな場では、同じ空気感のなかでアクティブに議論ができることがメリットだと思うので、マーケターとして成長していくためにも、そこを意識してほしいですね。
西野:対面でのコミュニケーションで感じる空気感やスピード感は、やはりリアルに勝るものはないと思います。オフィス出社とリモートワークのメリットを各自が考え、使い分けることで、「明日はOODだから、このタスクについては対面で確認しよう」など、日々の業務を戦略的にこなすこともできますよね。
オルビスの軸である「スマートエイジング®」の提供価値に立ち返りながら、シンプルに「お客様に最高のブランド体験をお届けするためには、何が最適か」ということを考え抜いて、ぜひハイブリッドワークを有効活用してほしいです。そして、今後も「ONE ORBIS」で新たな価値創造を目指す、オルビスらしい働き方に共感していただける方がジョインしてくれることを楽しみにしています。

いかがでしたか?
オルビスのハイブリッドワークには、「スマートエイジング®」の提供価値に基づき、社員一人ひとりが本来持つ力を多様に発揮し自分らしく働くことのできる環境を作りたい、という経営陣の想いが反映されていることが分かりました。
私(土井山)自身も、リモートワークが中心の働き方のなか入社した社員の1人です。オンライン・オフラインのメリットを存分に活用して、特に週1日のOODでは自らが社内の各フロアに足を運ぶことで生まれるコミュニケーションも大切にするなど、自分らしさを最大限に発揮できる働き方を模索していきたいと思います!
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
オルビスでは現在、一緒に働く仲間を募集しています。少しでも興味をお持ちいただいた方は、ぜひこちらからご連絡ください。 皆様のご応募、お待ちしております!
※本記事の情報は、公開日(2022年11月18日)時点のものとなります。
Profile
土井山 幸香(Doiyama Yukika)
2021年新卒入社、HR統括部 広報グループ所属。 広報担当として、オルビス公式ブログの編集、公式SNSアカウントの運用を行う。2022年より、サステナビリティ活動を推進するプロジェクトも兼務している。